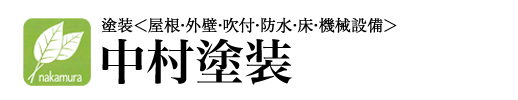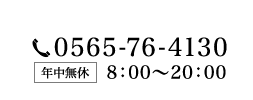年末のこの時期にお勧めしたい!家庭用高圧洗浄機でピカピカに
年末と言えば大掃除ですが、外壁や塀やコンクリートの床通路など家庭用の高圧洗浄機でも十分にきれいに洗い流す事ができます。そこで、洗う時のポイントはまず「自分に水が飛散するのでカッパや長靴を装着する」こと、「床と壁を洗う場合は床を先に洗ってから壁を洗う方が汚れを洗い流す手間が省けます」ことと、「汚れが周囲に飛び散るので特にお隣様の外壁や車などに飛散しないように洗う角度を調整したりブルーシートや段ボールなどで仮の飛散カバーのように使う」などでギリギリまで洗う事ができますね。
 コメント0件
コメント0件防虫剤塗料の効果を高めるには繰り返し塗り込むことが大事。
普通の塗料と違ってオイルステイン系塗料というのは塗膜を作るものとは違い木材に浸みこませて保護する塗料なので乾いては塗るの繰り返しで丈夫になっていきます。何度も塗る事で水弾きや害虫が入り込むのを防止する効果も高まりますが、臭いが強い塗料が多いので室内の塗装や犬小屋のようなものにはお勧めしません。塗装するなら臭いを抑えた水性系の防虫系塗料やオイルステイン系もあるのでお勧めです。
コメント0件ウッドデッキなどの防虫剤を塗る時に注意する事
ウッドデッキなどの木材の塗装をする時に注意することは塗料が水のようにサラッとしているので塗りやすいけど周囲に飛散しやすい事です。例えば木の板の塀を塗装する時に気を付けることは、板の真下は必ず垂れるのでシートなどの養生をしないと塗装後の飛散状態が大変なことになります。また、刷毛塗りでは塗料が伝って手元が汚れるので手袋などの装備を準備した方がいいです。防虫剤塗料(オイルステイン系塗料)は塗りやすい塗料でありながら余分なところまで色が浸み込みやすい塗料なので塗り方を考えて施工するようにしています。
コンクリート床に強靭な艶あり厚膜塗膜を作る
今日も工場内部での床塗装工事でしたが奥が深いと感じます。それは、厚い膜を作るには「一回塗りではできない」事と「気温に大きく左右される」事です。川砂のような珪砂と2液型のエポキシ系の専用液を混ぜて樹脂モルを作りコテで抑えてベースとなる下地を作り、中塗りや上塗りは厚膜専用の樹脂でコテで仕上げるコテ仕上げ工法です。これは相当難しいので床専門業者に依頼して施工する事が多いですね。
 コメント0件
コメント0件今日は久しぶりに雪が降りましたね。
今朝は久しぶりに雪が降って積もりましたね。今日は工場の内部塗装工事があり、行こうと準備していたら急に雪が積もってきたのでノーマルタイヤから大急ぎでスタットレスタイヤに交換して出発しました。家を出る前にはすでに5㎝ほど積雪があり現場までの道のりもアスファルトの色が見えないくらい積もっていたので下り坂はとても怖かったです。仕事の方は床塗装でしたが順調に施工できました。
コメント0件ケイカルの天井塗装に使用されるアクリル系塗料の効果とは
住宅塗装でも外部の天井によく使用されるケイカル板の塗装でアクリル系塗料を使用しますが、この塗料は凄い効果があります。それは「ケイカル天井板に対する密着性能と抜群の透湿性能」です。アクリル系塗料は外壁のような雨や紫外線に当たる場所では耐候性は劣りますが、天井のような場所では雨にも日にも当たらないので耐候性は必要ないですが密着性や防藻や防カビ性能もあるので天井塗装にとってはなくてはならない材料です。
コメント0件湿気の多い時に塗装すると艶に問題がでます。
ペンキの塗装と言えば艶ありの普通の塗装ですが、雨天のような湿度の高い時に塗装するとどうなるのか? それは艶ありの塗装しても時間が経つと艶がなくなって仕上がります。塗装して乾く途中に細かい水滴がのるとペンキと反応して艶がない状態で乾いてしまうからです。逆に艶消しの塗装では問題なく乾いて艶消し仕上げができますが、あまりに湿度が高い時では密着不良などの剥がれを生じることがあるので、できれば晴れて空気の乾いた環境で仕上げたいですね。
 錆止め塗装作業中 コメント0件
錆止め塗装作業中 コメント0件外壁塗装は寒い時に施工した方が長持ちする⁉
寒い冬の塗装工事は少し敬遠されがちという事はありますが、弊社が施工した現場を見て感じたことは「寒い時の方が乾燥しているので塗料もしっかりと乾いて丈夫な塗膜を作る事ができる」のではと思います。どこをみても変な剝がれ方をしている所もありませんし綺麗に艶も揃っているので問題ないと思います。冬は朝晩の冷え込みが強い分、作業できる時間は短くなり施工日数も増えますが、そのあたりのことを踏まえて頂ければ良い仕上げとなりますね。
 コメント0件
コメント0件破風板のペンキ塗装はなぜ剝がれるのか。それは塗料や環境に問題が。
住宅塗装でよく見かけるのは「破風板は剝がれている所」をよく見ます。ではなぜ剝がれるのか? それは木は伸縮しやすいからです。雨が降れば膨張して乾燥すると縮むので、塗装面は動きについていけずに剝がれを生じてしまいます。それに、昔の塗料は合成樹脂塗料が主流だったこともあり密着性もあまり良くなかったので剝がれやすかったのではと考えられます。現在の木材塗装のほとんどが浸透性の防虫剤系塗料が主流なので剥がれる事はないですね。
 コメント0件
コメント0件ウッドデッキを長持ちさせるために必要な事とは
ウッドデッキを長持ちさせるためには「とにかくこまめに何度も塗る事」です。デッキ材は木と木の組み合わせでできていると思いますが、塗装しても塗装できない部分「上の木と下の木の接している部分はどうしても塗料を塗りこむことは無理なので、雨で濡れて傷むところはそういったところから腐り始めます。最近では床の梁や板の部分はアルミ柱や人口木板など腐らない素材を使用するなど最初のコストはかかっても長い目で見たら結果的には丈夫な方が安上がりになるという事もあるので丈夫なものに変更してきてますね。
コメント0件カレンダー
最近のコメント
- コンクリートブロックなどの塗装もよくしますが、塗り替えの場合でブロック花壇の塗装があります。ブロック塀の花壇は見える部分の外側を塗装しますが、花壇なので雨も入るし水撒きもします。常に濡れている状態が続くので中から水分が蒸発しようと外側に水分が出てきて塗装の面を押し上げて剝がれるという事もよくありました。花壇の塗装をする時には水分を通過できる塗料(透湿性)を使用するなど剥がれにくい塗料をお勧めします。
- サイデイング外壁のクリア仕上げは模様面に釘が撃ち込まれていることもあり、その釘頭が壁色にタッチアップされて変色しているので、その部分は予め補修して埋めておくかクリア仕上げした後に補修するか悩みますが、実際には最終的に透明を塗ると外壁の色も少し濃くなるなど変化するので先に色を調合してタッチアップ塗りをするのは難しいのではと思います。
- コーキング目地も同じで、きれいな状態になるように仕上げています。きれいな表面に仕上げるにはコーキングの癖「コーキングを出してからどのくらいで表面が乾いてくるのか?コーキング打設後に目地のマスキングテープはどのタイミングで取ったらいいのか。全ては早め早めに処理することが大事でコーキングをコントロールするには相当難しいのですが、今までの経験を生かしてどの季節でもきれいに仕上がるように調整して作業しています。
- コケの除去剤を実際に使用してみましたが、コケにかけてすぐに枯れるというものではなく数日間かけてゆっくり効いてくるみたいです。また、コケ以外にもカビの発生の多いので、塀など高圧洗浄で洗えるなら洗い流した方が早いと感じました。
- 塗装仕上げの基本は「速く均等に塗り広げる」事が重要で、樋の部分では繋ぎ目までを通しで塗り広げることで艶も均等な仕上がりとなるので、途中で手を止めないように気を付けて仕上げています。
- 弊社ではサイディング外壁も臭いの少ない水溶性塗料を使用することが多く耐久性に優れた塗膜と汚れにくい低汚染型の塗料(関西ペイント・トウペ)を使用しています。もちろん艶あり塗料と艶消し塗料があり、水弾き重視では艶あり塗料を推奨、和風の日本作りのお宅では艶消し塗料の落ち着いた空間作りなどお勧めしています。
- 古くなった屋根材(波板)は手で触ってみると分かりますがとても脆く少し手で押さえただけでもパリッとひび割れが出ることがあります。この場合は屋根の寿命なので台風が近づくこの季節は早めに取り換える事をお勧めします。強風で隣接お宅に飛んでいくとご迷惑おおかけしてしまう事もあるので早めの対応をお願いいたします。
- 厚膜塗装仕上げ通常よりも塗膜が分厚い分、施工単価も高くなりますが、耐久性が強いので車の駐車スペースやリフト走行などもできて硬い仕上がりとなります。
- 普段は雨の予想が出ている場合は塗装以外の養生(ビニール貼り)や清掃や下地処理など雨がいつ降っても大丈夫のように体制を整えてます。
- 屋根塗装の場合はある程度材料をまとめて練り合わせる(2液型塗料)ので、材料の効果反応を少しでも抑えるために材料は日陰に置くなど保管場所も考えて作業しています。