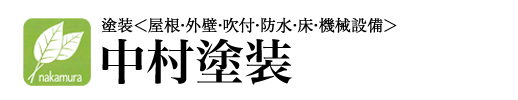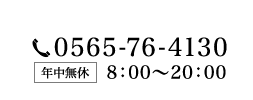室内の塗装作業では「照明」が大事です。
室内の塗装は外で塗るのと比べてかなり暗いので見にくく作業しづらい事が多いです。最近ではLED照明でも花形に開く投光器がありめちゃくちゃ明るく細かい部分の色分けやダメ込み・塗り継・垂れなどの確認も楽々に行えます。また、消費電力が少なくて済むので同じものを2~4つほど使用して日中のような明るさにして工場などでも内部塗装に最適です。電源のとれない時でもポータブル電源を持っていけばどこでも使用できますね。
コメント0件今日は床塗り塗装の奥深さを知りました。
今日は工場内部の床補修塗装をしました。今回は塗膜の厚いいわゆる「厚膜塗装」のひび割れクラック補修をしましたが簡単にはいきません。目地から入ったクラックが真っ直ぐに入っている場合はあまり気になりませんが、ジグザグにひび割れたり放射状に割れたりすると真っ直ぐなラインに目地を入れて直すのがとても大変です。下地が常に動いているのでひび割れがなくなるという事はありませんが、ひびが入っても気にならないような補修ができれば最高なんですけどね。
コメント0件外部スレート屋根塗装は洗浄と下塗りは欠かせません。
工場や農機具倉庫など最近はこの上に板金で被せるカバー工法は多いのですが、塗装で維持できる場所もあり塗り替え工事で屋根の表面強化と水の流れもよい方がコケが生えにくいですね。屋根塗装にもはや必須の高圧洗浄と、スレート系屋根は下塗りのプライマーはできれば塗りたいですね。この手間だけでも耐久性はかなり延長しますし見た目もいいです。スレート屋根の劣化の激しい所では洗浄時に飛散する水しぶきを囲い養生するなど手間もかかりますが周囲への配慮も大事なのでご迷惑を可能な限りかけない施工が大事です。
コメント0件油のしみこんだ鉄骨に塗装するには
油が浸み込んだ鉄骨の塗装の現場がよくありますが、何の処理もせずに塗装できるかと言ったらできない事はないですが、塗装した後にその塗装した面が不具合を起こして剥がれるなんてこともあるので下地処理は絶対大事です。今回の場合は鉄骨に付着した油を分解しないとこれから塗装する塗膜がうまく密着しないので洗浄作業や拭き取り作業が必要になります。普通に塗装するよりも手間がかかりますが後々の事を考えてしっかりとやっておいた方が良いですね。
コメント0件床の厚膜塗装のメリットとデメリット
厚膜塗装はたくさんの材料を使って塗膜の分厚い塗装仕上げができて表面がフラットでツヤツヤな硬い塗膜の仕上がりが最高にいいのですが、デメリットとしては材料がたくさん必要となるので施工単価が上がります。あと、表面が硬くなるので塗装面のコンクリートにヒビがある場合は塗装しても同じようにヒビが入るのでヒビの目立ちにくい暗い色の塗装をお勧めしています。
 コメント0件
コメント0件内部の鉄骨の手すりにウレタン塗料を塗って仕上げたらベタベタする
鉄骨手すりの塗り替え塗装で主に内部の塗装になりますが、塗装した翌日から手すりを持って階段の上り下りをしていると何か違和感を感じていました。それが塗装した部分がベタベタと粘りを感じるいわゆる「ベタツキ感」です。これは普通の建物に塗る塗料「ウレタン塗料・シリコン塗料」などを塗った時にこのように感じます。これが外部であれば雨に当たったり埃がのったりとベタツキはほとんど感じないでしょう。内部でベタツキを軽減できる塗料としては昔からあるペンキで乾きの遅い自然乾燥型の合成樹脂塗料は大丈夫なようです。
コメント0件ベランダ部分の塗装やシート防水劣化も早めの対応が大事ですね。
ベランダ部分の劣化塗装依頼が増えています。ベランダ部分は屋根と同様に劣化が進みやすい場所なので早めの対応が長持ちの秘訣といえるでしょう。セメント系のベランダでは臭いの少ない速乾塗料で施工する事が多く、FRP床では耐久性重視の溶剤系塗装をメインに施工しています。シート防水の場合は施工方法がたくさんありますが剝がさずに施工する方法もあります。シートの場合はどうしても熱による縮みがあり引っ張られて変形してしまいますがシートのヨレが気にならなければ空気抜きの脱気栓取り付け施工で敷くことができ、漏水防止になると思います。
コメント0件遮熱塗料に耐候性がプラスされた遮熱フッ素仕上げ
夏になると屋根の塗装が多くなり遮熱塗装を塗りますが、その遮熱塗装の中でも耐候性のランクがそれぞれあります。ウレタン系やシリコン系やフッ素など、またその材料が1液型なのか2液型なのかによっても耐久性や価格ももちろん変わります。このように材料が変われば施工価格は変わりますが塗装する物の劣化状態によっても価格は変わります。屋根がサビサビなのか錆が出てないのかによっても作業工程や施工仕様も変わるので一概には言えませんが、ただ早めに施工する分にはいいので建物年数が10年を過ぎたら考えて頂きたいですね。
 コメント0件
コメント0件モルタルベランダ床を水性塗料の防水材で補修することも
モルタル床の補修塗装をすることが多いのですが、塗り替えの場合は前に塗ってあるのがどんな材料かわからないので不具合が起きない安全な水性塗料仕上げをしています。その施工のメリットは臭いが少なく塗装後の乾燥も早く次の工程にと時間の短縮にもなります。また、雨が降っても心配のないように滑り止めの標準仕様となっているので安心ですね。
 コメント0件
コメント0件錆の状態により掃除の仕方や塗装工程も変わります。
鉄骨塗装など錆が出ている状態によりケレン方法(清掃下地処理)や塗装方法(錆止め材や上塗り材の材料選定)など状態に合わせて塗装の仕方を変えています。鉄骨塗り替えの場合、塗膜の劣化の仕方が表面がパリパリしている場合では一般的な一液型の錆止め材でも大丈夫ですが、外部の場合ではさらに過酷な状況な場所ではさらに丈夫な2液型の錆止めを使用したり劣化部分のみ二回錆止めを塗ったりとちょっとしたことでも錆止めの効果を高めるので状況を素早く判断して適正な施工法をしています。
コメント0件カレンダー
最近のコメント
- コンクリートブロックなどの塗装もよくしますが、塗り替えの場合でブロック花壇の塗装があります。ブロック塀の花壇は見える部分の外側を塗装しますが、花壇なので雨も入るし水撒きもします。常に濡れている状態が続くので中から水分が蒸発しようと外側に水分が出てきて塗装の面を押し上げて剝がれるという事もよくありました。花壇の塗装をする時には水分を通過できる塗料(透湿性)を使用するなど剥がれにくい塗料をお勧めします。
- サイデイング外壁のクリア仕上げは模様面に釘が撃ち込まれていることもあり、その釘頭が壁色にタッチアップされて変色しているので、その部分は予め補修して埋めておくかクリア仕上げした後に補修するか悩みますが、実際には最終的に透明を塗ると外壁の色も少し濃くなるなど変化するので先に色を調合してタッチアップ塗りをするのは難しいのではと思います。
- コーキング目地も同じで、きれいな状態になるように仕上げています。きれいな表面に仕上げるにはコーキングの癖「コーキングを出してからどのくらいで表面が乾いてくるのか?コーキング打設後に目地のマスキングテープはどのタイミングで取ったらいいのか。全ては早め早めに処理することが大事でコーキングをコントロールするには相当難しいのですが、今までの経験を生かしてどの季節でもきれいに仕上がるように調整して作業しています。
- コケの除去剤を実際に使用してみましたが、コケにかけてすぐに枯れるというものではなく数日間かけてゆっくり効いてくるみたいです。また、コケ以外にもカビの発生の多いので、塀など高圧洗浄で洗えるなら洗い流した方が早いと感じました。
- 塗装仕上げの基本は「速く均等に塗り広げる」事が重要で、樋の部分では繋ぎ目までを通しで塗り広げることで艶も均等な仕上がりとなるので、途中で手を止めないように気を付けて仕上げています。
- 弊社ではサイディング外壁も臭いの少ない水溶性塗料を使用することが多く耐久性に優れた塗膜と汚れにくい低汚染型の塗料(関西ペイント・トウペ)を使用しています。もちろん艶あり塗料と艶消し塗料があり、水弾き重視では艶あり塗料を推奨、和風の日本作りのお宅では艶消し塗料の落ち着いた空間作りなどお勧めしています。
- 古くなった屋根材(波板)は手で触ってみると分かりますがとても脆く少し手で押さえただけでもパリッとひび割れが出ることがあります。この場合は屋根の寿命なので台風が近づくこの季節は早めに取り換える事をお勧めします。強風で隣接お宅に飛んでいくとご迷惑おおかけしてしまう事もあるので早めの対応をお願いいたします。
- 厚膜塗装仕上げ通常よりも塗膜が分厚い分、施工単価も高くなりますが、耐久性が強いので車の駐車スペースやリフト走行などもできて硬い仕上がりとなります。
- 普段は雨の予想が出ている場合は塗装以外の養生(ビニール貼り)や清掃や下地処理など雨がいつ降っても大丈夫のように体制を整えてます。
- 屋根塗装の場合はある程度材料をまとめて練り合わせる(2液型塗料)ので、材料の効果反応を少しでも抑えるために材料は日陰に置くなど保管場所も考えて作業しています。