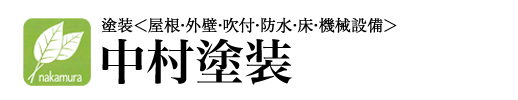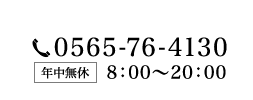急激な温度変化に注意して塗装しています。
気温の低い日が続いていますが、日中は風がなければポカポカと暖かく感じます。屋根の塗装では昼間の温かい時間で作業するようにしないと急激な温度変化に塗料が対応できず乾く前に霜が降りて本来の艶が出ないとか艶以外にも濃い色では白っぽく変色してしまう事もあります。この時期では塗装するタイミングをよく見極めて作業しないと塗り直しとなる事もあるので注意しています。
コメント0件朝の屋根上はとても危険。
屋根と言ってもいろんなタイプがありますが、その中でも注意しなければならない屋根は瓦屋根です。瓦でも大きく2種類に分かれますが、ツルツルしたタイプとザラザラしたタイプです。一般には普通の住宅はツルツルタイプでお寺のいぶし銀の瓦はザラザラしています。塗装工事で注意したいところはツルツルタイプで雨や水で濡れた部分を歩く時に屋根との摩擦が少なくなるのでとても滑りやすい状態となっています。私たちも工事中ににわか雨でも降ってきたら屋根からすぐ降りるようにしています。降りれなくなることもあるので十分に注意して作業しています。それに比べてお寺屋根タイプのザラザラ屋根瓦は雨で濡れても足元に気を遣わず問題なく作業できます。
コメント0件木材の自然の汚れはある程度きれいになる
木材の汚れ(自然に雨が当たったり紫外線で変色すること)はある程度きれいにすることはできます。専用のあく抜き材やしみ抜き材などを使って徐々に汚れを落としていきます。ところが専用液が劇物なので業者でないと手に入れることが困難ですし、作業手順や施工方法を知っていないときれいにすることができません。ペンキ塗りと同様で「ただ塗るだけは誰でもできるが、垂やムラなく塗るという事は難しい」という事があるように汚れを落とす手順を決めて均等に色ムラを抑えるなど何事も奥が深いのです。
コメント0件コーキングの劣化具合はそれぞれ異なる
コーキングが劣化して亀裂やひび割れがおきますが、コーキングの種類によって変わることはわかりますが素材の状態によっても亀裂のしかたは変わります。やはり下地が変化・変形する代表的なものはサイディングです。サイディングは伸び縮みしやすく、年数が経つと最終的にはかなり縮む傾向にあるので目地のジョイント部分は両側に引っ張られ大きく隙間が空いてしまいます。下地が動くものは普通の亀裂と違い傷みが激しいので劣化が大きくなる前に様子を見て打ち替えする方がいいですね。
 コメント0件
コメント0件足場に上がると見えない所がみえてくる
現場見積りから仕事の依頼を受けて足場を設置して塗装工事が始まりますが、同じ現場が一軒もないように現場の状況(周囲の状況・立地状況)によっても外壁の傷み具合やコケの生え方も違ってきます。足場の上で一日中作業していると下から見えなかったひび割れや隙間・陥没穴などより詳しくみる事ができます。逆に言えば見積りの時に見逃している所が沢山あるので、できるだけ足場のあるうちに補修・修繕工事が行えるようにその都度対応しています。
コメント0件冬の高圧洗浄作業
足場も組み終え外壁の高圧洗浄をしました。この時期の洗浄はとても厳しいですね。とくに外壁よりも天井部分では上向きに洗うので水滴が滝のように降り注ぎ逃げ場はない。雨カッパを着てても冷たいし、背中の部分は汗の逃げ場もなく蒸れて休憩時には体が冷えてとても冷たく風邪をひいてしまいそうになります。この時期は急激な温度変化が起こりやすいので体調管理に気をつけて作業したいですね。
コメント0件塗装用の足場を作る
今日は住宅用の足場の組み立てをしました。住宅と言ってもいろんな形がありますよね。平屋の低層から3階たての高層など、組み立てに真っ直ぐな正方形や長方形は組みやすいけど、入り組んだ部分があったり2階建てとは言いつつロフトがついてるなど、ロフトと聞いただけでも3階建てじゃない?とか思いつつ組み立てています。鉄の足場を組み始めてはや25年。もう四半世紀もやっているのだとしみじみ感じてしまいました。やっているといろんなことにぶつかります。玄関部分は通りやすいように邪魔にならない位置に設置するとか、シャッターガレージの部分は足場が当たらないように工夫するなど一つ一つ考えながら組み上げなければならず奥が深いとつくづく思います。
コメント0件冷たい雨と時々雪が舞いました。
今日は予想以上に冷たい雨が降りました。塗装工事は手先をよく使うのでしびれたり、指先の感覚がなくなったりとよくなります。住宅の場合はやはり家の角や屋根上は風がよく通るので体が芯まで冷えてしまいますね。また、屋根の上で一日中仕事している屋根屋さん・瓦屋さんは冬の冷たい風の中作業しているのでものすごく大変だと思います。しかも瓦の表面が凍っていることが多いので滑りやすく自然と足元に力が入り神経もすり減らして作業しているので大変なことです。
 コメント0件
コメント0件色の調合するときの注意点
建築塗装では色調合するときにはいわゆる原色の色で黒・赤さび色・黄色・白色である程度の色を作る事ができます。ですが、緑色系や青色などは別に紺色が必要ですが普段はあまり使いません。いつもはベースとなる色の3色を上手に混ぜ合わせて色を作ります。例えばアイボリー系の色は3色と白色を混ぜてバランスをとります。でも塗料は明るい色ほど変化しにくい(色が効きにくい)ので黄色は3色の中でも使用頻度も多くすぐなくなってしまいます。逆に黒や赤さび色は少しの量でも変化するので入れ過ぎてしまうと元に戻すことが困難になりますので注意が必要です。また、こげ茶色系の色に色味が濃いので薄くしようと白色を入れますが、意外と白色も少量で変化しやすいので油断できません。
コメント0件塗装工事に必要なのは・・・
塗装工事に必要なことは準備と段取りです。ただ塗装工事の塗装することは簡単ですが、周囲を汚さないように養生したり塗り替えの場合では下地処理をして剝がれないように塗装することです。塗装はただ塗ればいいだけというわけではなくて準備・段取りが8~9割りと言っても過言ではありません。しっかりと準備して施工すればきれいな仕上がりとなること間違いないです。
コメント0件カレンダー
最近のコメント
- コンクリートブロックなどの塗装もよくしますが、塗り替えの場合でブロック花壇の塗装があります。ブロック塀の花壇は見える部分の外側を塗装しますが、花壇なので雨も入るし水撒きもします。常に濡れている状態が続くので中から水分が蒸発しようと外側に水分が出てきて塗装の面を押し上げて剝がれるという事もよくありました。花壇の塗装をする時には水分を通過できる塗料(透湿性)を使用するなど剥がれにくい塗料をお勧めします。
- サイデイング外壁のクリア仕上げは模様面に釘が撃ち込まれていることもあり、その釘頭が壁色にタッチアップされて変色しているので、その部分は予め補修して埋めておくかクリア仕上げした後に補修するか悩みますが、実際には最終的に透明を塗ると外壁の色も少し濃くなるなど変化するので先に色を調合してタッチアップ塗りをするのは難しいのではと思います。
- コーキング目地も同じで、きれいな状態になるように仕上げています。きれいな表面に仕上げるにはコーキングの癖「コーキングを出してからどのくらいで表面が乾いてくるのか?コーキング打設後に目地のマスキングテープはどのタイミングで取ったらいいのか。全ては早め早めに処理することが大事でコーキングをコントロールするには相当難しいのですが、今までの経験を生かしてどの季節でもきれいに仕上がるように調整して作業しています。
- コケの除去剤を実際に使用してみましたが、コケにかけてすぐに枯れるというものではなく数日間かけてゆっくり効いてくるみたいです。また、コケ以外にもカビの発生の多いので、塀など高圧洗浄で洗えるなら洗い流した方が早いと感じました。
- 塗装仕上げの基本は「速く均等に塗り広げる」事が重要で、樋の部分では繋ぎ目までを通しで塗り広げることで艶も均等な仕上がりとなるので、途中で手を止めないように気を付けて仕上げています。
- 弊社ではサイディング外壁も臭いの少ない水溶性塗料を使用することが多く耐久性に優れた塗膜と汚れにくい低汚染型の塗料(関西ペイント・トウペ)を使用しています。もちろん艶あり塗料と艶消し塗料があり、水弾き重視では艶あり塗料を推奨、和風の日本作りのお宅では艶消し塗料の落ち着いた空間作りなどお勧めしています。
- 古くなった屋根材(波板)は手で触ってみると分かりますがとても脆く少し手で押さえただけでもパリッとひび割れが出ることがあります。この場合は屋根の寿命なので台風が近づくこの季節は早めに取り換える事をお勧めします。強風で隣接お宅に飛んでいくとご迷惑おおかけしてしまう事もあるので早めの対応をお願いいたします。
- 厚膜塗装仕上げ通常よりも塗膜が分厚い分、施工単価も高くなりますが、耐久性が強いので車の駐車スペースやリフト走行などもできて硬い仕上がりとなります。
- 普段は雨の予想が出ている場合は塗装以外の養生(ビニール貼り)や清掃や下地処理など雨がいつ降っても大丈夫のように体制を整えてます。
- 屋根塗装の場合はある程度材料をまとめて練り合わせる(2液型塗料)ので、材料の効果反応を少しでも抑えるために材料は日陰に置くなど保管場所も考えて作業しています。